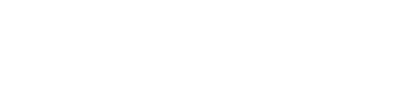今西錦司が紹介する森下正明
ヒマラヤ断念 代わりに蒙古めざす
ぐずぐずしているうちにヒマラヤの一番乗りを立教大学の連中がやってしまった。
ナンダコット(6867メートル)の登頂に成功したのである。しかしそのころの我々は、ヒマラヤに対してもっと大きなことを考えていた。
せっかくヒマラヤへ行くのなら六〜七千メートルの山ではつまらない。8,848メートルの世界最高峰エベレストに人類が登れるか登れないかということこそ、ヒマラヤのかかえている最も大きな問題なのである。
この間題を避けてはヒマラヤに行く意味が半減する。
ところがエベレストには1921年以来、英国山岳会がすでに何回も登山隊を送り込んでいる。いつ成功するかは別として、英国にすればエベレストだけはぜひ英国人に登ってほしいと思っていることだろう。
だから我々はこの間の事情をおもんばかり、1938年の目標には次善として世界第二位の高峰カラコラムのK2(8611メートル)を選ぶことにした。
そこで仲間の一人、伊藤忠君をきっそくインドに派遣してカラコラム入りの許可をとるよう奔走してもらった。
その年のヒマラヤンジャーナルのニュース欄に「来年は日本隊がやってくるだろう」と書かれていることからみても彼のインドにおける活躍ぶりがわかる。
しかし、六分の可能性が見えてきたときにまたもや、日中事変の拡大で計画がだめになってしまったのである。
一度目は満州事変で、二度目は日中事変で二度ヒマラヤ行きは流れ、またまたヒマラヤの代わりとして、こんどは蒙古に出かけることになった。
1938年の内蒙古調査隊の隊長は当時山岳部の部長をしておられた木原均先生にお願いした。
内蒙古は日本と違い、茫漠としてとりとめのないところだが、私はそこに魅力を感じた。
高さも魅力に違いないが、蒙古の魅力は土地の広がりが持つ魅力である。それはこの蒙古の草原をどこまでも西へ旅していったらいつかは
中央アジアに行けるという大陸の魅力なのかもしれない。
我々は実際内蒙古で、中央アジアかららくだはるばるやって来たという駱駝の隊商を見かけて、胸をおどらせたものである。
そのころはすでに英国との関係が悪化し、ヒマラヤ入りの許可を得るあてもなくなっていたから、二度にわたるヒマラヤ計画を進めてきた仲間も解散同然のかっこうになっていた。
世間は戦時色が強まり、騒然としていた。ちょうどそのころ、二十ほど年の違う若い世代が「ぜひ一つ、我々のリーダーになってほしい」と私を買いに来た。
川喜田二郎(移動大学業務理事)、梅樟忠夫(京大教授)、藤田和夫(大阪市大教授)、吉良竜夫(同)、伴豊(戦死)といった連中である。
私は徳田御稔君らと新たにつくった京都探検地理学会を母体として、西太平洋カロリン群島のボナペ島へこうした連中をつれて調査に出かけた。1941年のことである。
副隊長は当時昆虫学教室にいた森下正明君(京大教授)が引き受けてくれた。
スポンサーは木原先生が顧問のようなことをしておられた「南洋興発」という会社だった。
横浜からの長い船旅の間、我々は毎日デッキで講義の時間を持った。同じ船に乗り合わせた学者を講師に頼んだこともあり、私もまたカゲロウ研究のかたわら仕込んでおいた雑学を若い連中に伝授した。
ボナペ島で仕事をしているうち、こんどは日米の風雲があやしくなった。
ボナペ島からの最後の船で帰って来た。帰ってしばらくしたら12月8日、太平洋戦争 に突入したのである。
この帰りの船で船の位置を定めるために船員が天測をしているのを見て、「これはいける」と思った。
この天測を大興安嶺で使おうというのである。
東興安嶺探横行 ~食糧補給へ分隊作る~
いつごろからか私は大興安嶺を南から北へ抜けて黒龍江岸の漠河に至る探検の夢にとりつかれていた。
なぜ、それをやろうかと思ったかというと、当時満州でいちばん活躍していた満鉄調査部が、この大興安嶺踏破を二度試みて二度とも失敗していたからである。
これは山登りというより純然たる探検である。白頭山から内蒙古へ飛んだときもいつか満州でこの仕事をしてやろうと思っていたが、なかなか手ごわい相手なので、勝算を得るころまではいってなかった。
たまたまボナペ島からの帰途、船上で天測している船員を見て、直観的に天測を用いるならば大興安嶺だってやれるという自信が出来た。
そこできっそく船上で若い連中を集めて「おれには大興安嶺探検という三の宿題がある。
そいつをやるまでおれは枕を高くして寝られない。お前らもやるか」と協力を求めたところ「喜んでやろう」といってくれたので、では善は急げだ、来年やろうということになった。
それからスポンサー探しや現地との交渉が始まるのだが、なにしろ学生が主力だし、それに隊長も大学の一講師というのでは、現地の方でなかなか乗り気になってくれない。
これは普通のやり方ではだめだと気がついた。そこで仲間の一人、可児藤吉君(戦死)に「とにかく新京(現在の長春)まで行ってねばれるだけねばってくれ」と頼んだ。可児君は新京へ行ってくれた。
我々の計画に対し、交渉先の満州在留の軍当局が逆提案してきた計画は全く子供だましの腹の立つようなものだった。
可児君から連絡が来るたびに私は「原案で押し通せ」と返事した。こうして可児君は約一カ月日参し、たしか32回か3回目の交渉でやっと相手側が「それなら原案通り承認する」というところまでこぎつけてくれた。
あとは具体的な実施計画ということになって、無電士、測量士などは満州側から出してもらうことに決まった。
問題は漠河に到達するまでに要する食糧が膨大な量に達し、これを運ぶためにはまた運ぶものの食糧を加えなければならないというこの種の探険隊につきものの悪循環を、どのようにして断ち切るかというところにあったが、これは隊を二つに分け、一隊は逆に漠河から入って、本隊の食糧を補給するということで解決した。
そして、この漠河隊の隊長は、ボナペ島で副隊長をやった森下正明君に再びお願いすることにした。
そうなると広い大興安嶺の密林の中で、本隊と漠河隊とがどのようにして落ち合うのかという問題が、新たに生じてくるが、ここで初めて天測がものをいうのである。すなわち両隊とも定時に天測を行なって自分の位置を確認しておき、定時に無電連絡をしてお互いに「本日の位置東経何度何分、北緯何度何分」と知らせ合いながら、南と北から徐々に接近していけばよいのである。
またこのためにはボナペ島から帰ったあと、ただちに何人かの隊貞に天測の技術を習得させておいたのである。
もう一つ問題があった。それはどういう季節にこの探検を実施するかということである。夏を選んだ満鉄調査部が失敗した理卸は調べたところ二つあった。
一つは夏になると大興安嶺一帯が湿原になることである。この湿原は各地坊主といって、あしのような丈の高い革が株状になって生えている以外はすべて水におおわれてしまうので、人間なら株から株へ飛び移ってでも連れるが、馬も通れず、車も通れぬという状態になるのである。もう一つはそのころになると吸血性昆虫、蚊はもちろんのこと、アブ、プトなどがやたらに発生することだった。
冬季はもちろんすべてが凍結するので問題外とすると、最適の時期というのはだからその表面の凍結がゆるみ始めて、しかもまだ湿原が広がらず、アブや蚊の出て来ない早春以外にないと私は考えた。
ところが、その時期だとまだ草が芽をふいておらないため、馬糧をなにほどか持参しなくてはならなかった。1942年(昭和17年)3月、私たちは三河から興安嶺に入ることになった。
このあたりは白系ロシア人の開拓地だったので、私たちは彼らの馬を雇い入れ、出発時には25頭ほど連れて行った。アムンゼンは南極でいらなくなったそり犬を食糧にしたというから、荷物がなくなったら、その馬を食べることも考えてみたが、馬の持ち主たちがそれだけは勘弁してくれといった。
探検中には幸い一頭の馬しか倒れなかったが、その倒れた一頭でさえも彼らは食べてくれるなといった。
大興安嶺探検行~食糧補給へ分隊を作る~
馬など食わなくても、大興安嶺にはオロチョンという狩猟専門の土着民が住んでいたので、われわれはその連中に鉄砲を持たせて獲物をねらわせた。彼らはときどきハンダバンという大きな鹿を撃ってくれた。その内をゆでておいて、小出しに食べて旅行した。
また川にはタイメンがいた。満州にいる日本人はこれを興安まぐろ〃と呼んでいたが、身の色はまぐろのように赤くなくーむしろかじきに近かった。
しかし味はかじきより数等うまかった。このタイメンを釣るのは最近日本でも流行のリール釣りでやった。私はカゲロウの研究で始終渓流へ出かけていたので、あまご釣りにはよく出会ったが、そのころは研究が大事だというので釣りはやらなかった。
しかしカゲロウの方が一段落したころからあまご釣りを始めた。当時はいまと違って釣り人も少なかった。
京都から峠一つ越えたところに芹生というところがある。前の晩にそこで泊まり、翌朝から釣り始めて半日で軽く五、六十匹は釣れたものである。大興安嶺へも釣りざおは持って行った。
だが、あまご釣りのさおではとてもタイメンは釣れない。そこで同行したロシア人にリール釣りを教えてもらい、その道具を借りて釣っていた。
しかし、しまいには肝心のルア(擬餌針)がなくなり、タイメンの泳いでいるのが見えていても手が出せなくなった。
そこで私はいままでしまってあったあまご釣りのさおを出してきて小魚をねらって針を垂れた。たちまち20センチぐらいの魚がかかった。
"しめしめ″と引と、最適の時期というのはだから、その表面の凍結がゆるみ始めて、しかもまだ湿原が広がらず、アブや蚊の出て来ない早春以外にないと私は考えた。
ところが、その時期だとまだ草が芽をふいておらないため、馬糧をなにほどか持参さんがしなくてはならなかった。
1942年(昭和17年)3月、私たちは三河から興安嶺に入ることになった。このあたりは白系ロシア人の開拓地だったので、私たちは彼らの馬を雇い入れ、出発時には二十五頭ほど連れて行った。
アムンゼンは南極でいらなくなったそり犬を食糧にしたというから、荷物がなくなったら、その馬を食べることも考えてみたが、馬の持ち主たちがそれだけは勘弁してくれといった。
探検中には幸い一頭の馬しか倒れなかったが、その倒れた一頭でさえも彼らは食べてくれるなといった。
大興安嶺探検行~連絡用に無電を装備連絡用に無電を装備~
馬など食わなくても、大興安嶺にはオロチョンという狩猟専門の土着民が住んでいたので、われわれはその連中に鉄砲を持たせて獲物をねらわせた。彼らはときどきハンダバンという大きな鹿を撃ってくれた。その内をゆでておいて、小出しに食べて旅行した。また川にはタイメンがいた。満州にいる日本人はこれを”興安まぐろ”と呼んでいたが、身の色はまぐろのように赤くなくーむしろかじきに近かった。
しかし味はかじきより数等うまかった。このタイメンを釣るのは最近日本でも流行のリー.ル釣りでやった。
私はカゲロウの研究で始終渓流へ出かけていたので、あまご釣りにはよく出会ったが、そのころは研究が大事だというので釣りはやらなかった。
しかしカゲロウの方が一段落したころからあまご釣りを始めた。当時はいまと違って釣り人も少なかった。
京都から峠一つ越えたところに芹生というところがある。前の晩にそこで泊まり、翌朝から釣り始めて半日で軽く五、六十匹は釣れたものである。
大興安嶺へも釣りざおは持って行った。だが、あまご釣りのさおではとてもタイメンは釣れない。そこで同行したロシア人にリール釣りを教えてもらい、その道具を借りて釣っていた。しかし、しまいには肝心のルア(擬餌針)がなくなり、タイメンの泳いでいるのが見えていても手が出せなくなった。
そこで私はいままでしまってあったあまご釣りのさおを出してきて小魚をねらって針を垂れた。たちまち二十センチぐらいの魚がかかった。
"しめしめ″と引き揚げにかかったところ、大きなタイメンがうしろから来てパクツとその小魚をのんでしまった。
そしてあれよ、あれよという間に糸を食い切って逃げてしまった。天測のおかげ・で本隊と漠河隊とは、首尾よく予定した地点で合流することが出来た。
漠河隊はトナカイを連れて来ていた。このトナカイというのはおもしろい動物で、鹿の二榎だが、日本の鹿のように雄だけに、つのがあるのでなくて、雄も雌も両方ともつのを持っている。
馬もトナカイも昼は荷物を運ばせるが、夜は放牧しておくのである。
朝になると放しておいた馬やトナカイを探しに出かけるが、なかなか且つからぬ場合もあって、そのために出発が二時間も二時間も遅れることだってしばしばある。漠河隊と合流後しばらくはトナカイ、馬の両方を連れて歩いたが、馬のためには草の多いところで泊まらないとだめだし、トナカイの方は馬の食べる革には見向きもしないでもっぱら岩についた苔を食うものだから、どちらにも適した泊まり場を探し出すのにひと苦労した。
またトナカイが谷地坊主の上をすべるがごとく通り抜けるのには感心した。人間なら自分の踏むところを見とどけたうえで足を進雷ことが出来るが、四つ足の動物にどうしてうしろ足の踏むところがわかるのであろうか。
馬はそれが出来ないので谷地坊主の上を歩かせようとしてもすぐ水の中にはまってしまうのである。馬は乾燥地帯の動物であっても、湿地帯の動物ではない。
満州軍が私たちの計画に難色を示していたのは、大興安嶺が軍の守備範囲の外だったこととも関係があるらしい。
そこにはしかし匪臓もいなかったし、ソ連軍もいなかった。大興安嶺はいわば、戦争から絶録された場所だったのである。
のちにソ連軍が満州に侵入したとき、漠河の日本人は身動きがとれなくなり、一部の人たちが私たちの通ったルートを求めて脱出を囲ったと聞いているが、定かではない。
それにしてもこの大興安嶺では無電が完備していたため、空地連絡も非常にうまくいった。
あるとき軍の飛行機がきて慰問晶を投下してくれたのはよいが、あたり一面に散乱し、せっかくのウイスキーなども割れてしまった。
そこできっそく無電でハイラルに連絡し「あのような投下では意味ないからパラシュートをつけて放ってくれ」といったら、翌日もうl回飛んできて、こんどはウイスキーにもおもちゃみたいなパラシュートをつけて落としてくれた。
その夜は月が出た。「京都・東山に出た月みたいやなあ」などといって久しぶりの酒にみな上きげんだった。
再び蒙古へ~西北研究所長に就任~
大興安嶺探検は結局六十三日かけて成功した。この探検隊の主力が20歳前後の学生であったことは前にも述べたが、京大の学生ばかりでなくて、立命館や大阪商大(現大阪市立大学)の学生もいた。
また私が当時非常勤講師をしていた京都高等蚕糸学校からも三人の学生が参加していた。
のちにこの三人が藩第しそうになったので「この非常時に蚕なんかどうでもええやないか」といったらほんとうに学校をやめてしまった。
私もいらぬことをいったものである。しかし終戦後一人は南米に行き、あとの二人は幸い日本でそれぞれの仕事に精出している。昨年だったか大興安嶺探検30周年記念会を京都で催したが、昔忘れず集まってきた人たちが、みな大学の教授や会社の重役などになっていて、お互いにその健在を喜び合うことが出来た。
終戦後GHQが私たちの大興安嶺探検を知り、その資料を求めてきた。しかし、私は「これは学術調査のつもりでやったのだから公のものにしたい。
軍の秘密にされてはせっかくの努力が報いられない」と申し入れたところ、一米国人の世話で、米国でも一流の地理学会誌「ゼオグラフィカル・レビュー」に地図を入れた私の論文が発表された。
隊員が分担して執筆した日本文の報告書も原稿は出来上がっていたのだが、当時の世相ではなかなかこれを引き受けてくれる出版社はなかった。
何とか文部省に頼み込んで助成費を付けてもらい、毎日新聞社から『大興安嶺探検』と遺して出版されたのは、なんと探検から十年後の1953年だった。
なお全文ではないが、ダイジェスト版が最近に出た文芸春秋社発行の 『現代の冒険I、砂漠と密林を越えて』の中に収録されている。
申し遅れたがこの探検には、私の中学の同優生、奥平定世君(麗澤大学教授、当時は大阪商大教授)が終始協力してくれ、彼の顔で満州軍士の連絡もつき、また大阪の実業家からの経済的援助も受けることが出来たのである。
この"一興行″終わったあと私はしばらく休養するつもりでいたところ、またもやお座敷がかかってきた。蒙古善隣協会に新たに西北研究所というのが出来るから、その所長になってくれというのである。
だれが私をほんとうに推薦したのかいまだにわからぬが、三人も自称推薦者のあることを私は知っている。こんどの人選も森下正明、梅棹忠夫、中尾佐助(大阪府大教授)といった探検仲間に、新たに藤枝晃(京大教授)、甲田和衛(阪大教授)、野村正良(名大教授)など現在の第一線教授をずらりと並べた堂々たる陣容だった。
副所長にはいまは故人になられた石田英一郎さん(元東大教授)を迎えた。西北研究所は内蒙古の一つの入り口、張家口にあった。私は赴任早々、かねてやりたかった冬の蒙古の調査を半年ほどかけて実施した。
これは探検というほどのものではないにしても、馬やラクダを利用して自動車の入り込めない砂漠の内部や外蒙ぎかいを調査したのだから、私としてはああいう切迫した状況のもとでよくあれだけのことをやったものだと思っている。この調査行の中から私の“遊牧論?が生まれてきた。
それとともにいままでのカゲロウの研究では絶対に視野に入ってこなかった。動物社会における群れというものの存在を、蒙古人の放牧する家畜の群れや蒙古草原を彷律するカモシカの群れを通して体験することが出来た。
こ重ことは私のその後の学問の展開と深いかかわりがないとはいえない。蒙古にいると内地の厳重な報道管制と違ってどこからか情報が入ってくる。
ヤルタ会談のニュースなど、早くかち知っていた。軍隊の中にも八月十五日の終戦以前から「日本は負けるのと違うか」と問う兵士がいた。内地では私の留守家族も米や芋の買い出しに相当苦労していたらしいが、我々は幸い食糧にはなんの不自由もしなかった。
酒は自乾児(パイカル)という相当きつい地酒を毎晩飲んでいた。もし日本が負けなかったら、蒙古にいた私はとっくに胃かいようでバテていたかもしれない。